はじめに
最近、話題になっている佐藤航陽さんの『ゆるストイック』を読みました。
「努力はがんばるものではなく、仕組みで積み上げるもの」という考え方に興味を持ち、手に取ったのがきっかけです。
私自身、ブログやYouTubeに挑戦しているところなので、本書の前半では共感する部分が多くありました。
一方で、読み進めていく中で「この本は誰のために書かれているのか?」と、立場の違いを意識させられる場面もありました。
継続と挑戦の重要性には共感
前半では、「自分に合ったやり方で継続すること」や「運を引き寄せるには行動量が必要」といった考え方に大きく共感しました。
これは、私が今ブログやYouTubeに取り組んでいる中で、まさに感じていたことでもあります。
「完璧じゃなくても、とにかく続けること」
「特別な才能よりも、小さな積み重ねが大事」
という言葉は、自分自身の背中を押してくれるように感じました。
起業家的な視点と“共感”のズレ
ただし、後半に進むにつれて、少しずつ違和感を感じる場面もありました。
筆者の視点が「起業家」「実業家」としての経験に基づいているため、自由に環境を選び、自分のルールで動ける人を前提にしている印象があります。
私は福祉を学んでいることもあり、「相手の立場で考えること」や「選べない人の存在」に意識が向きます。
そうした立場から見ると、筆者の語り口には“強い人の視点”や“社会的に余裕のある人の前提”が感じられ、
「誰にでも通用する考え方なのか?」と少し距離を感じる場面もありました。
挑戦のハードルが高すぎる?
筆者は「挑戦は重要」と繰り返し述べていますが、その挑戦がどれもレベルの高いもので、
読者の中には「自分には無理かも」と感じる人もいるのではないでしょうか。
私はいま、ブログやYouTubeに取り組んでいますが、それはすでに大きな挑戦です。
だからこそ、「もっとハードルの低い挑戦例」が紹介されていたら、多くの人にとって実践しやすい内容になったのでは、とも感じました。
たとえば…
通勤中に一単語だけ英語を覚える 毎朝5分だけ日記を書く SNSで週1回、学んだことを投稿してみる
こんな小さな挑戦でも、立派な「行動」だと思います。
読者を選ぶような視点もあった
終盤の「インターネットが現実世界に近づいてきている」という章で、
「言語情報は伝わりにくい」「ここまで読み進めてくれた人は少数派」といった記述がありました。
読者としては、褒められているようにも感じましたが、同時に
「理解できない人はここまで来れない」というような、やや選民的な雰囲気も受け取りました。
そこには「知識や理解力のない人たちは自然と脱落する」という、皮肉のようなニュアンスもあり、
福祉の立場から見れば、「もっと寄り添う姿勢があってもいいのでは」と思ったのが正直な感想です。
デジタルツールへの前向きな姿勢には共感
一方で、本書の中で語られていた「新しいデジタルツールに触れてみるべきだ」という主張には大いに共感しました。
私も、こうしてAI(ChatGPT)の力を借りながらブログを書いています。
デジタルをうまく活用すれば、行動のハードルはぐっと下がりますし、それ自体が挑戦にもつながると感じています。
あとがきに込められた想い
本書のあとがきでは、「誰かの助けになれば」という筆者の想いが語られており、全体の印象が少し変わりました。
本編では少し強めに感じられた言葉の数々も、
「誰かを一歩踏み出させるための言葉だったのかもしれない」と思い直せた部分もありました。
おわりに
『ゆるストイック』は、自分の挑戦や継続について改めて考えるきっかけをくれた一冊でした。
ただ、やはり「言うは易く行うは難し」という言葉が浮かびます。
行動すること、継続することの大切さは理解できても、実際にそれを実行するのは簡単ではありません。
だからこそ私は、「いきなり完璧を目指すのではなく、自分なりの小さな挑戦を重ねていくこと」が大切だと思っています。
その一歩が、ブログやYouTubeでの発信でした。
本書を読んで少しでも前向きな気持ちになった方がいれば、
その気持ちを、ほんの少しの“行動”に変えてみてはいかがでしょうか。
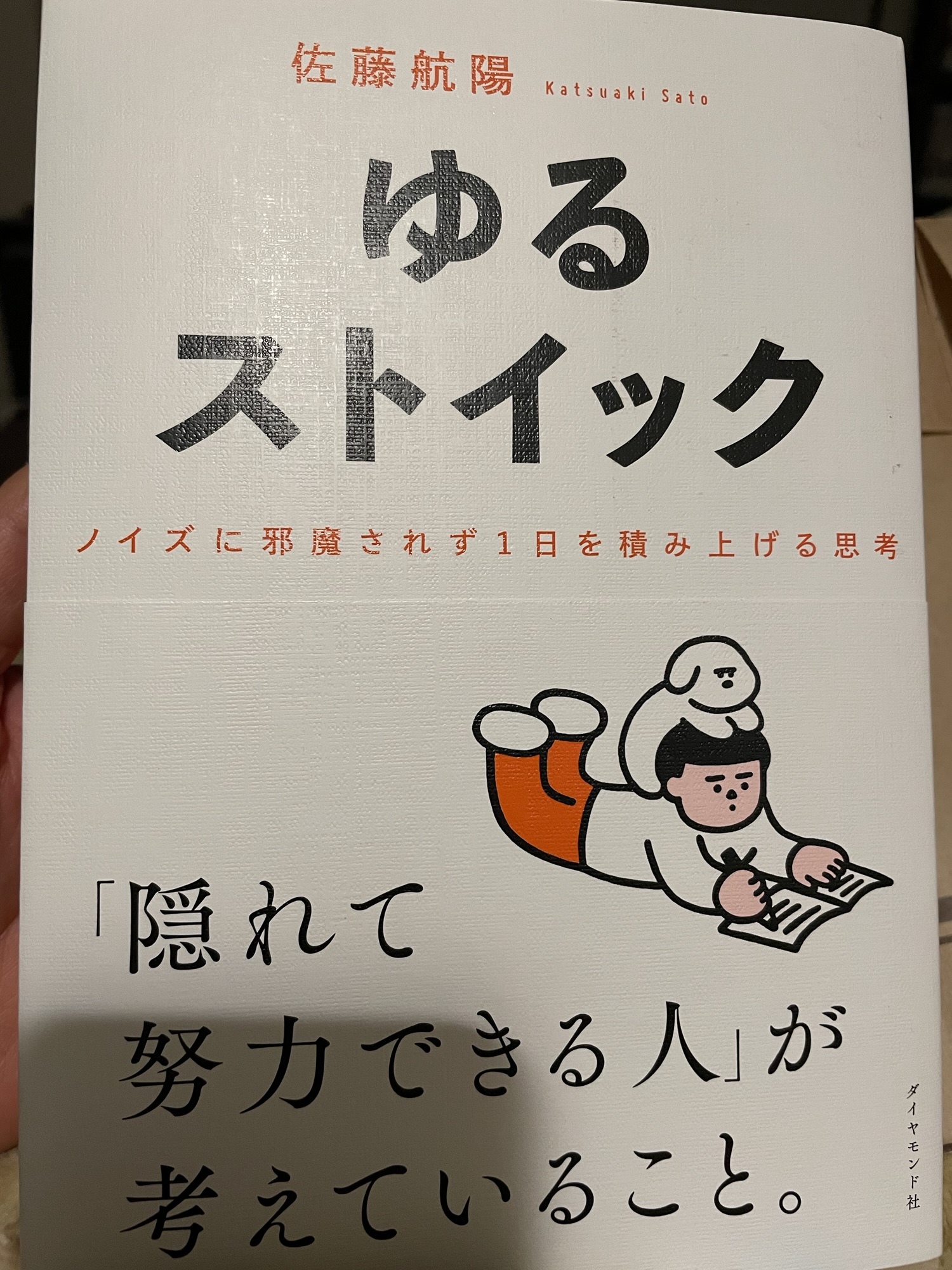

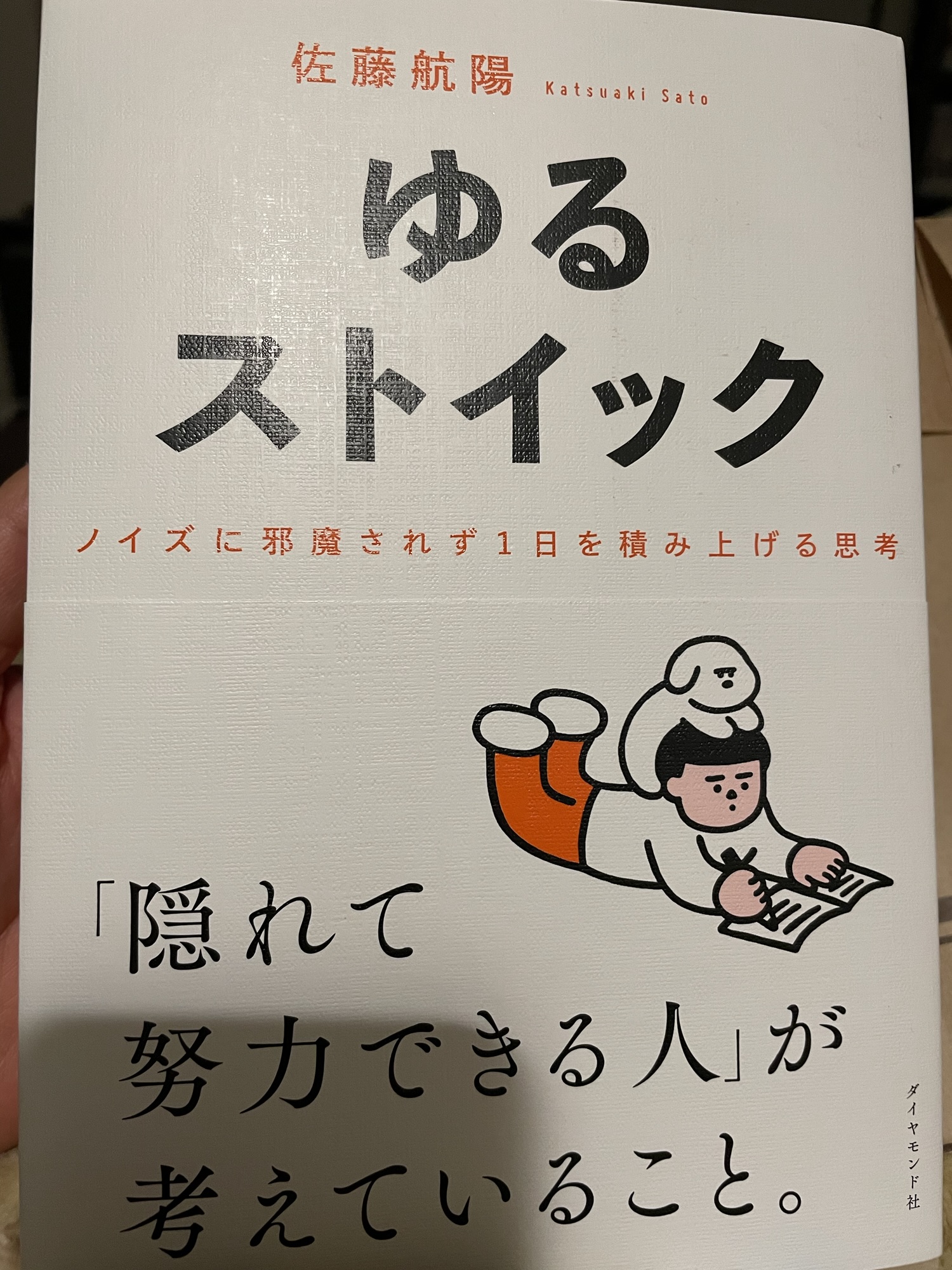
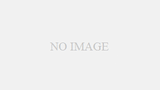

コメント