こんにちは。若オジです。
30代になってから、体のちょっとした不調に敏感になってきた私ですが、最近「薬膳」という言葉が気になるようになりました。
薬膳と聞くと、なんだか専門的で、漢方の知識や特殊な食材が必要な気がして、ハードルが高そうですよね。でも調べていくうちに、こんなシンプルな結論にたどり着きました。
「薬膳=特別な料理」ではなく
「薬膳=旬のものを食べて体を整えること」
つまり、普段の食事で“季節の野菜”を取り入れるだけでも、立派な薬膳になるということなんです。
■ そもそも薬膳とは?
薬膳は、東洋医学の考え方に基づいた食事法のこと。
簡単に言えば、「食べ物の持つ力を使って、体のバランスを整える」ことを目的としています。
ポイントは以下の通り:
病気の予防や体質改善を目的とする 体調や季節、年齢、生活環境に合わせて食材を選ぶ 「医食同源」の考えに基づいている(=食事がそのまま薬になる)
薬膳というと、漢方薬や難しい素材をイメージしがちですが、実はスーパーで買える普通の食材でも十分なのです。
■ 季節の野菜がなぜ薬膳になるの?
東洋医学には、「天人合一(てんじんごういつ)」という考えがあります。
これは、人間は自然の一部であり、季節や気候の変化に体も影響を受けるという考え方。
だからこそ、
春には春の不調に合った食べ物 夏には夏の体調を整える食べ物
を食べるのが自然なことなんです。
そしてそれこそが、薬膳の本質。
■ 実は日本の食文化って、もともと薬膳的
たとえば「土用の丑の日にうなぎを食べる」「夏に冷やしトマト」「冬におでんや根菜たっぷりの鍋」など、
昔から日本には、季節と体の関係を意識した食の知恵が根付いています。
つまり、私たちの祖父母の世代は意識せずとも薬膳的な食生活を送っていたとも言えます。
■ 薬膳に興味があるけど、難しそう…という人へ
薬膳の入門書などを見ると、「五性(熱・温・平・涼・寒)」「五味(甘・辛・酸・苦・鹹)」など、専門用語が出てきて少し難しく感じるかもしれません。
でも、最初はこんなふうに考えるだけでOKです。
□ 今の季節に合った野菜を選ぶ
□ 体を冷やしたいか?温めたいか?
□ 疲れているか?乾燥しているか?
この感覚だけでも、十分に薬膳的な選び方ができます。
■ 今日からできる簡単な薬膳的ごはん
春:菜の花のおひたし、たけのこご飯 夏:きゅうりとわかめの酢の物、トマトの冷製スープ 秋:れんこんのきんぴら、梨のコンポート 冬:大根と鶏肉の煮物、ごぼうたっぷり味噌汁
どれも特別なものではなく、家庭で簡単に作れるものばかり。
薬膳は「特別」じゃなく、「ふだんの食事をちょっと意識すること」でいいんです。
■ おわりに
薬膳という言葉を聞くと、つい難しく構えてしまいがちですが、
実は私たちが昔から食べてきた「旬を大事にした食事」そのものが薬膳に通じているんですね。
無理に知識を詰め込まなくても、
まずは季節の野菜を味わいながら、
「今の自分に合う食事ってなんだろう?」と、ちょっと意識してみる。
それだけで、日々のごはんが少し体にやさしくなる気がしています。


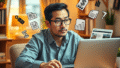
コメント